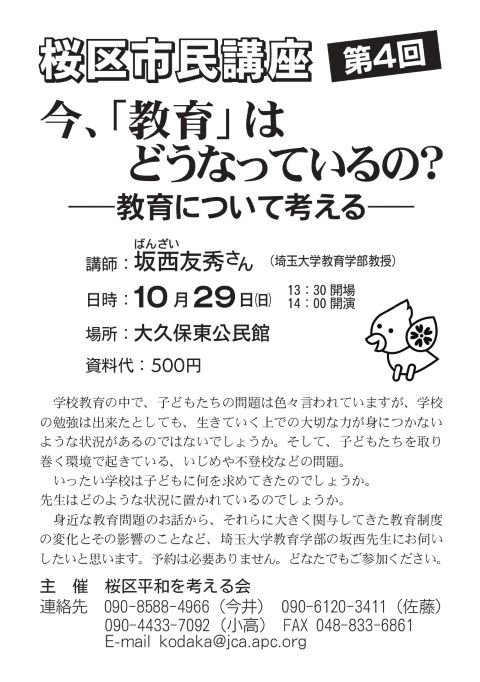 10月29日(日)、講師に埼玉大学教育学部教授の坂西友秀先生をお迎えして、市民講座を開催しました。
今の教育がおかれている状況についてお話を伺うことができました。
10月29日(日)、講師に埼玉大学教育学部教授の坂西友秀先生をお迎えして、市民講座を開催しました。
今の教育がおかれている状況についてお話を伺うことができました。
§外国籍の子どもの増加
外国籍の子どもの増加は、各国共通の現象です。現在進行形で起こっていることなので、対応は現場でしなければなりません。
フィンランドでは、教室に子どもたちの出身国の国旗を掲示して互いの理解を助けたり、言葉が通じないことを補うために絵などを使って工夫をしているそうです。
7〜8割が外国の子どもという実態が続いており大きなスケールで変化が起きているということでした。
§不登校
不登校は教育の基盤を揺るがす問題です。子どもたちは学校を通ってから社会に出るという仕組みになっているので、この問題は社会に大きな影響をもたらします。
不登校の子どもは健康状態の把握もままなりません。
また、周囲にうまく適応できない子どもたちも増えています。
発達障害が増えてきているということを文科省も認めるようになり、個に応じて教育を行うという方針になってきているそうです。
そのためには多様な子どもが一緒にいることはいいことだという了解が社会に認められることが必要ですし、教員も増やさなければ出来ません。
教育予算の裏づけが必要になります。手厚い対応が実現されることが期待されます。
§道徳教育の教科化の問題点
道徳の教科化について、一番に考えなければならないことは、道徳の目標を誰が決めるのかという問題です。
これが教科書の問題、評価の問題と直接つながってきます。
道徳は、内心・思想・宗教の自由にかかわることです。人間性と言い換えることが出来ます。
戦争中の修身教育の反省もあって、これまでは道徳教育はすべての教科の学習を通じて行うとして、教科化すべきではないとしてきました。
18歳から選挙権が認められたこととかかわって高校生の政治活動が注目されています。
学校の許可を得なければならないとか、休日に限って認めるなどの対応が出てきていますが、
この対応には、本人が力をつけて自分の生活を切り開いていくという観点が抜けてしまっています。
道徳は人間が人間としてまっとうに生きていくためのものです。
§大学の変化
そのほか大学に起こっていることとして、教授会が連絡機関化していることや、競争・評価が導入され、即、現場で役に立つことを要求されるなど、
すごいスピードで変化していっていることも指摘されました。
義務教育でも同じようなことが十数年前から起こっています。深く検討する必要がある問題です。

第4回桜区市民講座に参加して
埼玉大学教育学部の坂西教授の講座に参加しました。とても気さくな先生で大変楽しい時間を過ごせました。
欲を言えば、もう少し時間が欲しかったです。
これから学校の先生になろうとする学生さんを教える立場にある先生の話から、生の教育の現場を垣間見ることができました。
教育実習中に行方不明となった実習生を探し廻ったとか、苦労も多いようですね。
子どもの不登校(過去10年で最多の13万4千人超)、子どもの多様化・「発達障害」、いじめの問題。
フィンランドでは、不登校対策として「インターシップ」という制度があるそうです。
自転車が好きな生徒が働く自転車店を紹介していました。ここでは、「工作」の単位がもらえたり、料理を作れば、「家庭科」の単位がもらえたりとか。
もちろん学校へ行くことは必要なことですが、学校以外であっても「教育」に向き合っている姿勢に、こんな方法もあるのだなと感動しました。
<道徳>が「教科に格上げ」になるという話。(中教審が答申)
「教科」となれば、「教科書」、「目標」、「評価」とかが設定されて、その内容を”誰”が作るのかによっては大変なこととなるようです。
「道徳の教科書に載っていることが当たり前」の世界になってしまうからです。
普段はめったに聞けない「教育」の講座でしたが、難しいこともなく、参加して良かったです。
坂西先生、ありがとうございました。(会員Yさん)
|